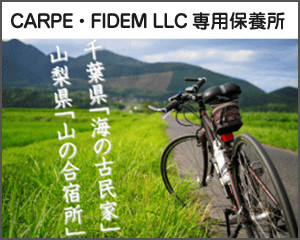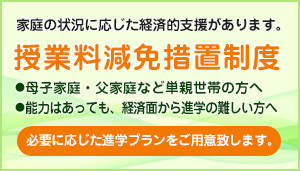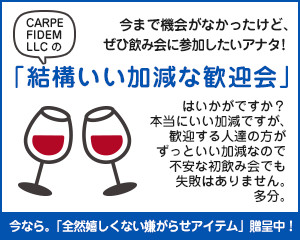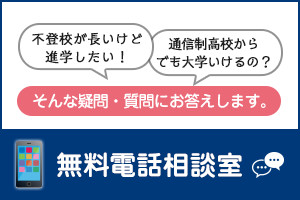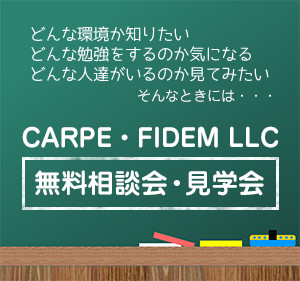「不登校対応という話だったのでその塾に入ったのですが、
内部は普通の高校生ばかりで・・・・・・」
新規参加希望者の子の話
「不登校専業」と、「ついでに不登校も」は別ものです。
不登校向け塾の選定ミスを回避するには
不登校 という問題自体は以前からありますが、今ではさほど切羽詰まったテーマとは認識されていません。環境さえ整えば、大半の不登校経験者が一般的な進学・就職ルートに復帰出来ることが判明しており、依然として課題はあるものの、10年20年前と比較すれば、困難の程度が目に見えて軽減されているためです。
ただ、進学ルートに復帰するにあたり、塾や家庭教師を利用した効率的な復帰手段が確保されている一方で、まれにその選定ミスにより、時間だけをロストしてしまうケースが見受けられます。通常の進学と比較し、不登校の学生さんの進学ルートは若干分かりにくいこともあって、小さな勘違いが大きな失敗に繋がることもあります。ここでは、そのようなミスが発生しないよう、最低限の注意点を挙げておこうと思います。
参照:不登校のまま何もしなかったらどうなるのか?
参照:不登校になったら何をすれば良いのか?
参照:不登校・引きこもりの原因とその対処実例 ~共感は本当に必要なのか?~
注意点1 「不登校・引きこもりをメインに扱っている塾か?」
至って当然の話ですが、世の中には専業と兼業があります。農家にも、専業農家と兼業農家があるように、不登校向けの塾にも、「不登校・引きこもり専業の塾」と、「普通の中高生の片手間に、兼業で不登校生を指導をする塾」があります。
どちらが良いかは、各家庭のニーズで変わってきますので特に言及しませんが、上記二者は「遅刻・欠席の取り扱い」で分かりやすく分岐します。
例えば、CARPE・FIDEMには個別対応の授業がありますが、当該授業では基本的に遅刻も欠席も自由で、特に事前連絡も要りません。いなければいないで、「まあ、何かあったのだろう」と判断し、自動的に別日に振替となります。遅刻したら遅刻したで、「なら、終了時刻をその分だけ延長しようか」となります。勿論、欠席でも遅刻でも、その分の授業料が没収になることはありませんから、費用が無駄になることもありません。
これは、不登校や引きこもりの経歴がある子達は、概して時間管理が下手なことが多く、時間設定を厳格にし過ぎると、全く授業に出られないまま授業料だけがドブに流れてしまうことがあるためです。平均的な不登校・引きこもり専業の塾なら、遅刻・欠席の取り扱いを緩くすることで、多少の不利益が自分達に降りかかることがあったとしても、その決定が、最終的には不登校当事者のためになる現実を深く認識していますから、遅刻や欠席程度で授業料を没収することはありません。逆に、不登校専業を謳っていながら、遅刻・欠席で没収授業になってしまう塾は、何かが根本的におかしいと判断しましょう。少なくとも、不登校当事者のためにはなっていませんし、彼等の事情を理解しているわけでもないでしょう。表面的に不登校救済を主張するだけで、実態はただ営利優先に走っているだけの可能性もあります。何故か授業料がはっきりしなかったり(ウェブサイトに授業料の掲載が無い等)、何かと理由をつけて追加請求が来るような塾には、くれぐれも気をつけましょう。
無論、いつまでも遅刻・欠席を許すのは間違いです。社会一般の常識では、時間管理は当然のことですし、自己責任の範疇です。しかし、それはそれで少しずつ成長すれば良いだけの話。当人達の成長を考えるなら、多少不利益があろうとも、一定の猶予を与えて成長を見守るのも支援側の義務ではないでしょうか。
以上のように、「最低限の誠意のある不登校専業の塾は、遅刻・欠席でも没収授業にしないし、急な振替でも無料で柔軟に対応している」。この点だけ憶えておけば、不登校からの塾選びの基本は、まず問題無いでしょう。
注意点2 「学習のスタートを柔軟に選ぶことが可能か?」
一般に、不登校の始まりは早くて小学生低学年から、遅いもので高校三年生と、年齢で見ても10年以上の開きがあります。どの分野であれ、学習は基礎からの丁寧な積み重ねが大切ですから、小学生の頃から続く継続的・断続的な不登校なら、仮に何歳であったとしても、小学生レベルから開始するしかありません。一方、中学校受験や高校受験を経由して進学校に進んだ子なら、基礎をスキップして応用から開始することも出来ます。
また、高校は高校でも、中高一貫の名門校の場合もあれば、大学進学などほとんど念頭にないような教育困難校の場合もあります。たかが偏差値の違いですが、されど偏差値の違い。その差は、学習面で大きな違いを生みます。
そのため、不登校から塾選びをする際には、学習のスタート地点を柔軟に変更出来るか否か、言い換えるなら、自分の躓いたポイントから再スタートして貰えるか必ず確認しましょう。
例えば、駿台予備校や河合塾、東進ハイスクール等の大規模な予備校等は、模擬試験や指導経験から養われた様々な受験情報を確保しているだけでなく、講師の先生方も実績豊富で優秀な方が多く、その面でのサポート体制は万全です。大手の予備校の強みは、まさにこの点にあります。
一方、生徒数が多く、教室等の固定費が大きいため、授業の進度や内容は一律にパッケージ化されており、生徒の側でシステムに合わせるしか手段がありません。
「18歳だけど、中学生の英語がまだ苦手で・・・・・・」
のような状況でも、そこから再スタートするような仕組みにはなっていません。
「ここは高校の範囲を勉強するところだから、自分で復習しといてね。頑張ってね」
でおしまいです。当たり前と言えば当たり前なのですが、厳しい現実です。
また、欠席時の補講が出来ない等、小さなところまで丁寧に配慮して貰うことはほぼ不可能です。
「欠席は自己責任であり、責任は自分で負いなさい。社会もそうなってるでしょ?」
でおしまいです。これも、当たり前と言えば当たり前なのですが、厳しい現実です。
一般的な学校もシステム運営されていますから、そこでドロップアウトした学生さんが一般的な予備校に馴染める可能性は低く、大体が一ヶ月程度で力尽きるようです。要は、「システム負け」です。
そのため、教育ルートが一元管理でシステム化された大規模な予備校は、何かとトラブルの多い不登校経験者にはかなり不利で、順当な成長を見込むなら、各個人単位でオーダーメイド調整を行ってくれる環境を選ぶ必要があります。無論、最終的には自分からシステムに合わせないといけない訳ですが、それまでの準備段階では、ある程度甘めの設定がないと危険です。
以上のように、どの学習段階からスタートしても、教える側で柔軟に修正を認めてくれるような学習環境を優先しましょう。
注意点3 「学習のゴールは自由に選ぶことが出来るか?」
この場合のゴールとは、
「どの大学へ進むか?(高校受験の場合は、どの高校へ進むか?)」
を意味します。
先に述べたように、不登校からの塾選びは学習のスタートが肝要ですが、それを満たす塾は全体的に小規模になりがちです。結果として、理系に強いが文系に弱い、文系に強いが理系に弱い等、塾毎の癖が顕著になる傾向にあります。
例えば、CARPE・FIDEM LLCの参加者は大体が理系進学希望で、一部社会学や経済学等の中間地点系に進む人もいますが、文学部等の「ザ・文系」学部への進学はほぼゼロです。理由は単純で、この手の学部は就職先が営業職であることが多く、不登校経験者の就職先として不利なためです。
参照:不登校・引きこもりと就職事情 ~就職出来ない人達に足らない要素~
「進学したけど、大学出たらNEETです」
なんてのは悪いジョークですが、実際、不登校経験で文系学部進学者には、この傾向が強く出ます。比較的人付き合いが得意で、20歳までに大学進学が出来るなら問題ありませんが、21歳過ぎor人付き合い苦手な場合、文系学部進学は極めて危険であり、全く意味の無い行為です。親類縁者による縁故採用が確定している、或いは卒後は起業予定である等の事情が無い限り、絶対にやめて下さい。
以上のような事情があるため、CARPE・FIDEM LLCでは、指導経験の結果として、ほぼ全て理系学部進学or理系科目からの経済・教育他社会学系学部への進学に収まっています。
ただ、これは文系進学を検討している20歳以下の学生さんや、元々人付き合いの得意な不登校経験者や、「どうしても文系学部に行きたい!」という学生さんには厳しい話です。それぞれのニーズがあるのですから、それはそれできちんと見なくてはいけません。医学部や獣医学部、薬学部等の医療系専門学部、早慶・MARCH等の私大理工系学部、東大・東工大他、国公立理工系学部等へ進学したいなら、CARPE・FIDEM LLCは良い環境ですが、「数学なんて絶対やりたくない」という人には、全く向いてない環境です。
このように、不登校からの塾選びには、最終的な進路先が自分の希望通りのものになっているのか、きちんと確認しなくてはなりません。進路先がズレていると、どこかで進路先の変更を余儀なくされたり、塾を変更しなくてはならなくなります。合格実績を確認するのも有効です。同時に、就職先が整備されているのか、事前の下準備をきちんとしておきましょう。
注意点4 「不登校とは別に、対等な友人付き合いが出来る環境か?」
仮に不登校になっても、何らかの環境で「ただ勉強するだけ」なら、難しい問題は存在しません。家庭教師の先生でも十分に可能ですし、場合によっては、親御さんが先生の代わりをすることも出来るでしょう。
しかし、「年齢に応じた友人関係を持ち、対等な関係でコミュニケーションを取る」という訓練は、近しい友人がいる場所でないと出来ません。対等な友人とは、勉強同様に重要な意味を持ちます。不登校関係の話題で、
「うちの子は、お兄さんやお姉さんのような、目上の人間としか付き合えないのです」
という話をよく耳にしますが、これは「対等な関係」を恐れているが故のことです。「対等」というものは中々に難しい立ち位置で、常時自分の自尊心が脅かされる可能性を秘めています。相互の力関係が同レベル故、お互いの距離感や上下関係その他の要素が複雑に絡み合い、「勝った負けた」の勝負に陥る特有の面倒臭さがあります。
しかし、そのような「勝った負けた」のような程度の低い関係が昇華された後こそ、深い相互理解が生まれます。目上の人間からの手加減含みの関係しか構築出来ないのは、その精神が未熟だからでしょう。最終的には、どこかで「対等な関係」を経験しなくてはならないのですから、逃げ回っていても仕方ありません。
中には、「勉強だけしていれば良い」と開き直るケースもありますが、明白な判断ミスだと理解しましょう。
「大学には受かったけど、結局ボッチで退学しました」
なんてのも悪いジョークですが、「勉強だけしてりゃいいじゃん」のような浅慮な勉強至上主義者は、しばしばこのような重大事を無視したがため、結局は惨めな状況に追い込まれます。人付き合いを疎かにした報いが、大学や高校進学後にやって来るのです。
以上のような事情により、先生としか会話する機会の無い塾は要注意です。その場その場では良くとも、合格したその後の段階から、取り返しのつかない悲劇に見舞われる可能性が極めて高くなります。とりわけ、一見すると不登校向きに見える個別対応形式の指導はトラブルが多く、入学後の環境について行けず、中退して引きこもりに戻る事例が多々発生しています。くれぐれも気をつけましょう。
参照:「不登校には個別指導が良い」は本当か? ~不登校に理解のある先生が生み出す新たな引きこもり~
勉強は勉強で重要です。しかし、不登校経験者は、概して人付き合いが下手で、足りない部分を改善しなければ、結局どこかで潰れてしまいます。大学進学後のことを考えれば、塾に在籍している段階で、同時に人間関係も克服しておく必要があります。
参照:不登校・引きこもりからの勉強は、仲の良い友人を作ることから
注意点5 「塾在籍中に、不登校で喪失した経験幅を広げることが出来るか?」
不登校になると、経験幅が著しく低下します。体育の授業が無いため体力が低下する点。文化祭が無いため、共同作業を行う経験を失う点。修学旅行が無いため、友達との旅路さえ知り得ない点。
少し挙げるだけでも、結構な差が出てくることが分かります。100%は難しいかも知れませんが、この差を多少なりとも埋めることが出来れば、進学後の負担も大幅に軽減させることが出来ます。
CARPE・FIDEMでは、定期的に希望者を募って旅行へ行きます。ある年の夏は八丈島でダイビングや大型魚の釣りを行い、ある年の冬は富士山麓でスキーやスノーボードに行きましたが、これもその活動の一環です。また、塾内部で起業グループを作成し、実際に社会に向けてサービスを提供するチームを編成したりしています。
或いは、千葉県に古民家を一棟購入し、何年もかけてゆっくりと改装作業を行っています。外房での荒海での海釣りも経験出来ますし、里山の野生動物との強制的なふれあいもあります。山梨県の山間部に大規模な合宿所を整備し、定期的に別環境での学習やバーベキューを楽しんだりもします。季節によっては、渓流釣りや、ぶどう狩りも良いでしょう。成人し、お酒の善し悪しが分かっているメンバーには、関係者専用のワインセラーやラウンジも用意されています。
参照:ワインセラーとバー・ラウンジのある大学進学塾 「CARPE・FIDEM LLC」
形式は様々ですが、何かしらこのような活動があるなら、「ただ勉強だけして終わり」という、退屈な生き方にはならないでしょう。部分的ながら、学校の代替手段としての機能を持ち合わせていることは、サブテーマとして望ましい要素です。特に、これからの時代は、自主的な活動を自分の頭で考えて実行することが求められます。小さいことのようですが、この積み重ねは馬鹿に出来ません。
注意点6 「指導者側の人生観は不登校支援に向いているか?」
「類は友を呼ぶ」と言いますが、何らかの判断を行う際にどのような人間を選ぶのか、そして、その結果が成功に結びついているのか否かは、常時定期的に判断を行う必要があります。男女間の仲でも、一見するとまともそうなのに、どういう訳かつきあう毎つきあう毎、全てどうしようもない相手を選んだりする人がいますが、これは判断そのものが歪んでいることの具体例でしょう。判断の結果が毎回失敗に終わっているとするなら、その判断自体が、言うなれば、本人そのものが歪んでいるのかも知れません。
同様に、何かを学ぶ際、その指導者の実態が掴めないのは好ましくないと言えます。顔が見え、どのような経験があり、どのような考えを持っているのか。これからどのようなことを行い、どの目標へ向かっているのか。それら一つ一つをきちんと対話出来ることが望ましいでしょう。ある程度の年齢があるなら、自己判断も出来るかも知れませんが、難しい場合には、親御さんが判断するしかないこともあると思います。
何事にも言えることですが、「選ぶ」という行為には、選ぶ人自身の人格が如実に表れます。どの環境を選ぶかも、選ぶ側の能力を反映しています。そう考えれば、
「まあ、別に適当なところで良いか。どうせ勉強するだけだし」
という、失敗確定の判断に陥らずに済むでしょう。
指導者の顔が見えるか否かは、大変重要なことです。実際に誰が自分に教えてくれるのか? どのような内容のことをどのような形式で伝えてくれるのか? それら全てを確認した上で、進路先を決めるようにしましょう。
以上、六項目。最低限ですが、確認を怠らないようにしましょう。これらを大筋満たしているなら、基本的にはどこであっても問題無いはずです。いつの時代でも、求める人には、それなりの解答が待っています。不登校は大変な問題かも知れませんが、解決不可能な程困難なことでもありませんし、どうしようもない程切羽詰まった問題でもありません。
気長に気軽に考えて、しかし、判断は生真面目に。
を心掛けましょう。