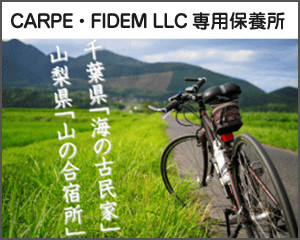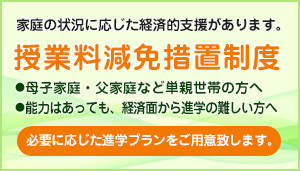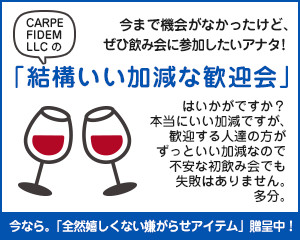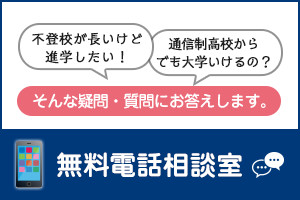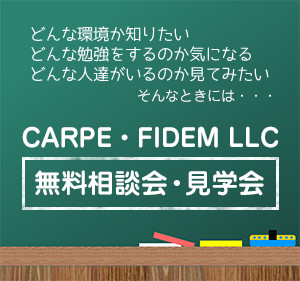「 引きこもり の親の会に行ったのですが、何故か補助金の話と政治の話、
障害者支援のような話ばかり出て来るんですよ。行くところ間違えたのでしょうか?」
数年前の相談事例
注:2013年2月上旬より、当コラム他複数のコラムについて幅広くご意見を賜りました。ご意見に対する回答を末尾に掲載致しましたので、ご希望の方はそちらもご覧下さい。但し、現実的視点に立脚したご意見が多いことから、長期高齢当事者の方や、その関係者の方、感情的な方の閲覧はお薦めしません。
30歳以上の長期高齢引きこもりに関する相談から(2023年11月更新)
Q1:息子は30過ぎの引きこもりですが、やれば出来ると思います。
A1:やれば出来る子は、30過ぎて引きこもったりしません。
Q2:昔は勉強も良く出来て、良い子だったのです。昔に戻りませんか?
A2:戻りません。諦めて下さい。あなたにとっては可愛い息子でも、世間的には薄汚いだけの落ちこぼれ中年です。現実を見て下さい。
Q3:社会人の弟が、引きこもりの兄を悪く言って困っています。私が庇っているのですが・・・・・・。
A3:弟さんが正しいです。親族に引きこもりがいれば、弟さんの結婚にも支障が出ますし、人生も壊されます。庇う方がおかしいという認識を持って下さい。
参照:「結婚相手の親族に、引きこもりという「負」動産がある場合の注意点1 ~失われる多額の財産~」
Q4:息子(中卒 45歳 職歴無し)を福祉(ここでは生活保護)に繋げようと思うのですが。
A4:どうぞご自由に。少子高齢化で若手の子達が必死で働いて支えている社会に、「無駄飯食いのお荷物」を押しつける意味を良く考えた上で。
Q5:では、どうしたら良いのですか?
A5:叩き出せばひとまず解決する問題を、あれこれ理由付けしてそうしなかったのは親側の無策です。無策の責任を取りましょう。
Q6:無策の責任を取るとは?
A6:世間様に迷惑をかけないことです。家の金が尽きたら、引きこもりは潔く死ぬ。それなら、誰も何も言いません。
Q7:生活保護はダメなのですか?
A7:国民の権利なのですから、どうぞお気軽に。一時的なトラブルから立ち直るために活用されている方も大勢いますし、寧ろ素晴らしい制度です。ダラダラと生活保護に依存したり、変なデモに参加する卑しい人達もいますが、息子さんがそうならないと良いですね。
Q8:息子は発達障害の診断を受けています。
A8:それは大変ですね。
Q9:発達障害だから引きこもりなんです。
A9:発達障害でも仕事して自立している人は大勢いますし、寧ろそっちの方が多数派ではありませんか?
Q10:発達障害で引きこもりの何が悪いのですか?
A10:別に悪くありませんよ。引きこもりの原因を発達障害に押しつけて、己が義務を放棄する人間は卑しいと思いますが。
Q11:発達障害だから仕事出来ません。
A11:「○○だから××出来ない」という論法はよく聞きますが、そんな無能力な人間は社会で使い物にならないじゃないですか? 必要なのは、「○○だけど、××出来る」です。発想を根本から変えて下さい。
Q12:発達障害でも仕事している人ってどんな人ですか?
A12:A11にある「○○だけど、××出来る」を大切にして、自分のやれることを地道に実行している人です。立派だと思いませんか?
Q13:何故子供がここまで引きこもり続けるのか、原因が分かりません。
A13:親側が適宜強制力を出さないためです。外圧も無しに居心地良い環境(実家)からわざわざ抜け出し、社会の中で自立しようなどと考える人間は少数派です。大多数の人間には、外部からの圧が必要なのです。強制で構いませんので、追い出して下さい。
参照;「引きこもり と強権的な親について ~強制力の強い親は本当に悪いのか?~」
Q14:家族会で、「子供との対話と傾聴が重要」と聞きました。「強制するのはダメ」だと。
A14:では、その対話と傾聴で状況は改善しましたか?
Q15:一時的に改善しましたが、また元に戻りました。今35歳で、暴力もあります。
A15:なら、もう諦めて下さい。10~20代なら対話でも上手く行きますが、30以降は効果が薄く、40過ぎではほぼ改善しません。無駄です。特に、暴れる引きこもりは碌な人間ではありません。
Q16:どうしていれば良かったのでしょうか?
A16:多少改善したなら、その段階で実家から出し、仕事をしないと死ぬ状況に追い込んで下さい。親子関係が多少変わった程度では、長期高齢引きこもりは脱ヒキしません。
Q17:それで死んでしまったらどうするのですか?
A17:どうもしません。運命と思って、弔ってやって下さい。
Q18:あまりに無責任ではありませんか?
A18:そうですか? 逆に聞きますが、何故ご子息が中年以降も平穏に生きていられると思っているのですか? 長期高齢引きこもりの生きる術など大してないのに、引きこもりを許し続けたことの方が、遙かに無責任だと思いませんか?
Q19:自分としては、子供のためを思ってやってきました。
A19:その結果生まれたのが、社会に順応出来ず、自立も出来ず、迷惑にしかならない存在です。現実には、子供のためになどなっていません。親が子の未来を考えずに問題を先送りし、子の死を恐れるがあまり、義務を放棄しただけのことです。はき違えてはいけません。
Q20:子供に死ねということですね?
A20:子供の前に、まずあなたが親として人間として成長して下さい。今の発言だけで、いかにあなたが未熟な存在か理解出来ませんか? 子供の死を他人のせいにしたいのなら、どうぞご自由に。
Q21:兄弟に引きこもりがいます。追い出したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
A21:追い出す側で徒党を組み、引きこもりを孤立させて下さい。数と腕力で負けないようにすることが第一です。徒党は親族でも知り合いでも何でも良いですが、徒党の代表者は、「引きこもりが死んでも構わない」と強く思える人が良いです。
Q22:それはやり過ぎではありませんか?
A22:実際にやってみれば分かりますが、中年以降の長期高齢引きこもりは、それ位でないと変わりません。
Q23:それで死んでしまったら?
A23:A17を参照して下さい。殺しはダメですが、気持ちで負けないようにするには、憎しみと殺意が最も有効です。
Q24:出した後のことについてはどうしますか?
A24:ボロボロで構いませんので、家を一軒用意し、まとまった現金(理想的には100万前後)だけ渡して、そこに送り込んで下さい。家賃と光熱費だけは、自立するまで親側で出して下さい。(この話は長くなるので、後日別に掲載します。)
Q25:引きこもりの姉がいます。高齢の親と同居していて、親も手伝いの名目でお金を渡しています。ただ、いつも家が汚く、手伝っているようには見えません。姉は本当に手伝いをしているのでしょうか?
A25:ほぼ嘘でしょう。雑な書き方ですが、以下を参照にどうぞ。基本、引きこもりの「親の介護してる」は90%嘘と見ておくと間違いありません。
Q26:40過ぎて就活もしない兄への怒りが止まりません。このまま親の資産を食い潰すだけなのでしょうか?
A26:40過ぎの長期高齢引きこもりの場合、何かの適性を期待するのはほぼ無理で、アルバイトが出来れば100点満点です。ただ、実家生活&アルバイトだと、自宅という逃げ場所があるため、それさえ続きません。継続させたかったら、Q21のような実家追い出し戦略と平行して下さい。
参照:不登校・引きこもりと就職事情 ~就職出来ない人達に足らない要素~
Q27:親が引きこもりの兄ばかりを優遇します。相続でも兄を贔屓しそうで嫌になります。
A27:典型的なダメ親ですが、親を批判すると更に厄介なことになります。経験則ですが、引きこもりを許すタイプの親は、相続でも引きこもりを特別扱いします。兄弟姉妹で等分に持ち込むのが理想ですが、引きこもり優遇の相続になってしまった場合は、「引きこもりの世話は今後一切見ない」という条件を徹底して下さい。資産を食い潰したら、ほぼ確実に無心が来ます。
Q28:贔屓を無くす方法はありませんか?
A28:面倒かも知れませんが、親との接点を増やし、相談者さんの方が親にとって有益かつ必要な存在であることをゆっくりと示して下さい。親の引きこもり優遇は、他の兄弟姉妹が家を出てしまい、結果的に引きこもりとの接点が増え、それが寂しさ解消に繋がっているためです。親の支持を得るようにして下さい。
Q29:長期高齢引きこもりの自殺の話は聞きますか?
A29:あまり多くはありませんが、引きこもりネットワーク繋がりで稀に聞きます。細かな顛末は言えませんが、残された家族が明るく元気になっている点だけは、ほぼ全ての事例で共通です。
Q30:人が死んで明るいというのは酷いと思います。
A30:逆に考えて下さい。家族にとっては、それ位引きこもりが厄介で疎ましい存在だったということです。綺麗事を言うのは容易いですが、それよりも引きこもりによる加害がどれ程家族に悪影響を与えているのか、まず認識して下さい。
Q31:引きこもりを合法的に自殺に追い込む方法はありませんか?
A31:あるわけないです。何言ってるんですか。ただ、同じことを思っている家庭は案外多いことを知っておいて下さい。
Q32:引きこもりの家族会に10年近く通っていますが、状況が何も変わっていません。
A32:具体名は言いませんが、恐らく手遅れ系家族会でしょう。そこは、補助金獲得のための活動実績が欲しいだけで、個別の事例への対処能力はほぼ無いです。家族会の中心で、最も条件の良い環境でも、無職学歴職歴無し40歳以上が延々と滞留しています。早々に離れて下さい。
Q33:子供が長年引きこもってはいるのですが、家事や買い物等の小さな手助けは率先してくれています。ただ、子供のことを考えるなら、家から出した方が良いでしょうか?
A33:基本的には出した方が良いのですが、手伝いがきちんと出来る引きこもり(と言うのが適切かは微妙ですが。)は実はかなり稀少です。今後の介護その他で協力が得られるなら、同居を継続しても良いと思います。
Q34:子供を長期の引きこもりにしたことは、確かに親のせいだと感じています。引きこもり家族会のシンポジウムにも参加しましたが、他責の空気が強く、好きになれません。
A34:それが普通の判断です。2010年前後はまだマシでしたが、最近は左翼系人権活動家の溜まり場になっています。「第○○回○○○全国大会 in ○○」のようなものには、近寄らないことです。
Q35:長期高齢引きこもりの親と、それ以外(引きこもりにさせない親)との違いは何ですか?
A35:A13にあるように、日常から小さな強制力を維持しています。強制の方向性は家庭によりますが、これまで見た中では、
「○時~○時の間(学校の時間等)は絶対に家にいることを許さない」
「家にいても良いが、家族の家事を行うこと」
「学校に行かないなら、最低でもアルバイトをすること」
等のような、何らかの条件を入れ、子供の希望を100%通すことはせず、必ずハードルを課しています。子供にとって、「家を居心地悪くすること」が大切です。
Q36:なら、30過ぎの息子に、親が食事を出すのはおかしいでしょうか?
A36:論外です。「働かざる者食うべからず」は何かと批判されがちですが、ここを曖昧にすると引きこもりは長期化します。「死にたくないなら自分で稼げ」「家を提供して貰っているだけありがたく思え」「いつまでも実家にいるな」で十分です。
Q37:気持ちとしては、子供に強く当たって追い出したいと思っています。ただ、自分の力ではどうにもなりません。
A37:親御さん側で決意が固まっている(引きこもりが死んでも構わない)なら、方法はいくらでもあります。(これも長くなるので、別に掲載します。)
Q38:大学に行くと言って、もう30歳過ぎです。勉強はほとんどせず、参考書だけが山積みになっています。予備校も行かず、ずっと自宅浪人です。このまま続けさせて良いのでしょうか?
A38:もう大学の件は止めさせて下さい。一般論ですが、頭の悪い学生程書籍だけが増えます。山積みの参考書は、そのまま当人の才能の無さを表しています。
Q39:相続についてです。子供3人で、長男が引きこもり、他2人(弟・妹)は結婚して子供もいます。自立していない長男に多く配分したいのですが、どうでしょうか?
A39:止めて下さい。必ず揉めます。このような事例の場合、ほぼ確実に、弟さんと妹さんの配偶者は、長男の引きこもりを良く思っていません。均等に分け、わだかまりが発生しないようにして下さい。(A3も参考にして下さい。)
Q40:上手い配分などはありますか?
A40:一般的な例ですが、「引きこもりに不動産を、他に現金を」という形式が上手く行きやすいです。可能なら、不動産は早々に売却して、引きこもりは小さい別の家(安い中古住宅が無難です。)に移し、別生活をさせるのが良いでしょう。絶対にやってはいけないのは、引きこもりの世話を他の兄弟姉妹にさせることです。「金が尽きたら死ぬ。それが嫌なら働け」を徹底させないと、兄弟姉妹の諍いを生みます。
Q41:引きこもり家族会で、「引きこもりにはお小遣い(月3~5万)をあげるように」とアドバイスされたのですが、これはいつまで与えれば良いのでしょうか? 子供は今32歳で、10年程あげ続けています。
A41:今すぐ打ち切って下さい。常識的に考えて、30過ぎて小遣い貰う大人がいますか? 本来なら、子供や甥姪にあげる立場ではありませんか? 引きこもり家族会の非常識なアドバイスについては定期的に相談が来ますが、無視して下さい。
Q42:子供が長期の引きこもりです。自分の子供ながら、殺したくなる感情が日増しに強くなります。おかしいとは思っているのですが、感情を止められません。
A42:それは普通の感情で、親御さんは悪くません。(悪い点があるとするなら、子供を追い出さなかった点だけです。)一定以上の年齢になったら、自立して旅立つのは子の義務ですが、それを試みず親への依存を続けるなら、それは子供の怠慢です。ただ、殺したいというのは正常な感覚ですが、現実には殺しは出来ません。喧嘩をしても縁が切れても構いませんので、追い出しを検討しましょう。(引きこもり追い出しについては、別コラムに掲載します。)
※以下は、2010年前後までの状況をまとめた、2013年段階での古い記事になります。
Q1:子供の引きこもりに、親の責任ってありますか?
A1:きっかけ自体には、特に無いことが多いです。しかし、長期化は親の責任であることが多いです。
Q2:親の責任は半分ということでしょうか?
概ねそんなところです。子供が引きこもったからといって、親御さんが自らのことを嘆く必要はありませんが、引きこもりをいつまでも黙認するのは、嘆くべき行為です。
Q3:何年以上を長期化と見た方が良いですか?
A3:3年以上だと、十分長期化です。
Q4:子供が引きこもったら、すぐに止めさせた方が良いですか?
A4:誰でも悩む時期はありますので、「すぐに」という必要はありませんが、長期間の引きこもりは許すのはお薦めしません。復帰の可能性が想像以上に低下します。
Q5:長期化する子供の特徴ってありますか?
A5:性格的なものとしては、「自分に甘い」「打たれ弱い」「逃げ癖がある」「思い込みと現実とのすり合わせが出来ない」「対人関係が苦手」「プライドだけは高い」「理屈をこねるが、実践はしない」などがあります。
Q6:家庭的な特徴や、環境などは?
A6:どの家庭でもあり得ますので目立った特徴はありませんが、あえて言うなら父親が弱いケースや、家庭全体が理不尽な思い込みやこだわりを持っているケースが目立ちます。環境については、部屋にインターネット環境があると長期化することが多いです。
Q7:もう少し具体的には?
A7:「親への暴力は許さない!」「○○歳までには家を出ろ!」のように、「この一線以上は認めない!」と強く言える存在が無いと、大体は漫然と長期化します。また、「正社員でないと認めない!」のような時代錯誤の家庭も問題です。
Q8:ネットは使わせない方が良いですか?
A8:そんなことはありませんが、部屋に回線を引かせると長期化しやすいです。リビングルームなどに設置し、家族共用程度にした方が良いでしょう。
Q9:中学生の頃から不登校で、高校も行っていない18歳の子供がいるのですが、今後自立させる上でどうしたら良いでしょうか?
A9:その場合には、まず「まともな仕事は無い」という現実を知っておいて下さい。厳しいようですが、今の時代、無教育層の若者は社会から必要とされていませんし、今後も必要とされないでしょう。勉強し直すか何かで、再度まともな教育のルートに戻らないことには、自立への道はほぼゼロです。
Q10:子供の引きこもりを止めさせられる親と、長期化する親とでは、どのような差がありますか?
A10:見た感じではっきり分かるのは、親の人生哲学と、発言の積み重ねが違います。
Q11:もう少し具体的に言うと?
A11:前者は、
「30歳までには必ず自立すること。それ以上は、どんなことがあろうと家から追い出す」
「自立するのは当然の義務。25歳までは準備期間として認めるが、それ以上は絶対に認めない」
のような線引きがしっかりしていると同時に、子供が幼いときから自立の重要性をきちんと語っています。一方で、自立するためのサポートも行っているため、子供もそれに合わせて行動します。
Q12:後者は?
A12:後者は、そういった親としての哲学がなく、漫然と、
「困ったなあ……」「どうしよう……」
のように言うだけで、人間としての芯が無く、かと言って、復帰へのサポートも適当です。(特に、父親がこのパターンの場合だと非常に厄介です。)そのため、子供も適当に引きこもり生活を続けることになります。或いは、「弁護士としての生き方しか認めない!」のように、どう見ても奇怪な要求を押しつけるような親の場合もありますが、これは論外です。
Q13:「引きこもりの親殺し」などの殺人事件などがニュースになりますが、うちの子供もそのような危険人物になるのでしょうか?
A13:何もせずに放っておき、完全に詰んでから強引に外に出そうとすればなるでしょう。
Q14:暴力事件は珍しいことではないのでしょうか?
A14:長期化事例では、ニュースにならないレベルの暴力沙汰などは日常茶飯事です。殺人事件、傷害事件予備軍は、特に珍しい存在でもありません。
Q15:何故そのような悲劇が起こるのでしょうか?
A15:単純に、問題を先送りにし続けた結果が、事件に結びついているだけのことです。「詰んだ状態」が暴力を引き起こす温床であり、ある日突然爆発した家族からの叱責や罵倒が、事件の引き金になっています。加齢と共に「詰んだ状態」は加速しますので、「詰んで」いれば、いつでも事件になる可能性はあります。
Q16:「詰む」の基準ってありますか?
A16:大体、何もしないまま30歳を過ぎると、まともな仕事の受け入れ先が消滅するので、9割方詰みます。20代の間にどれだけ行動したかで、大体が決まります。
Q17:家庭内暴力はやはり異常なことでしょうか?
A17:引きこもりでなくとも、思春期は何かと葛藤がある時期ですから、10代等、思春期のものは極端に構える必要はないでしょう。但し、「やられるがまま」などというのは論外です。
Q18:年齢的には、どれ位以上が問題なのでしょうか?
A18:現場感覚的には、30前後になっても暴力沙汰を犯しているのは、流石に成長が遅過ぎです。25歳以上の家庭内暴力は、それなりに異状と見てよいです。
Q19:子供が40歳等の中年になるまで、何もせず引きこもっていた場合どうなるのですか?
A19:どうにもなりません。
Q20:どうにもならないとは?
A20:そのままの意味で、「社会に出るルートが完全に閉ざされる」ということです。残念ですが、各家庭の優劣が表面化しただけのことです。
Q21:それぞれ事情があるのですから、優劣とかで比較するのは間違っていませんか?
A21:建前上はそうでしょうが、現実には家庭の優劣ははっきり存在します。「皆それぞれだよね」「比較は良くないよね」という意見は、表面的には心優しい響きを持っていますが、問題解決能力は皆無です。手遅れになった家庭は、どこかしらその種の「甘さ」を共通して持っています。
Q22:優しいことの何が悪いんですか?
A22:「優しさ」をはき違えている点です。引きこもりの現場でよく聞く「優しさ」とは、単なる「表層的な誤魔化しのための優しさ」です。表現を変えているだけで、詰まる所「先送り」に過ぎず、長期的には欠点にしかなりません。問題解決能力のある家庭は、自分の家庭のおかしいところをきちんと修正していますが、解決能力の無い家庭程修正を嫌がり、「皆それぞれ論」「優しさが大切論」などの、抽象的な話に逃げる傾向にあります。
Q22:動きたくても動けないお子さんもいるのではありませんか?
A22:残念ながら、もうそんな発言が通用する世の中でないこと位は分かるでしょう。誰も何も言いませんが、動けない人は、動けないまま終わっているのです。確かに配慮は大切ですが、現実を無視した配慮は、陳腐な傷の舐め合いにしかなりません。
Q23:引きこもりの親の会で、国が何とかすべきだという意見もありましたが……。
A23:親の会は複数ありますので、どこかは分かりませんが、それは「手遅れになった引きこもり当事者の親の会」でしょう。
Q24:「手遅れの親の会」なんてあるのですか?
A24:表面的には標榜しませんが、「事実上手遅れ」というものがあります。手遅れになってどうしようもないから国の支援を当てにせざる得ない状況であり、ある意味「手遅れの最前線」です。ただ、現実的有効策はほとんど出ていませんので、そういった歪んだ主張をしなくて済むよう、事前対策を講じておいて下さい。
Q25:「手遅れの親の会」には、何か特徴などはあるのですか?
A25:会によって違う部分もあるかと思いますが、各会に関与した人々の話をまとめると、大筋以下のような特徴があります。
A:親が60歳過ぎ、子供が30歳過ぎが目立つ
B:家庭の責任や親の責任よりも、国や社会状況に責任転嫁する話が中心になる
C:変なところで妙に団結しており、政治活動に結びつける傾向がある
D:支援サイドに福祉関係者が多い
E:国や地方公共団体からの補助金の話がしばしば出て来る
などの様子が見える場合には、「手遅れの親の会」のことが多いです。
Q26:Aは年齢的に手遅れということですか?
A26:そういうことです。見ての通り、年齢的にタイムリミットぎりぎりです。
Q25:Bの責任転嫁とは?
A25:そうするしか他に方法が無いため、鬱憤晴らしも兼ねてそのような論調が増えるためです。会全体から「親は悪くない!」的な臭いがする場合は要注意です。
Q26:団結は分かるのですが、政治活動なんてあるのですか?
A26:しばしば聞く話です。本当に手遅れになり、「どうしようもなくなったから政治的に解決を!」という発想です。これが嫌で「親の会を抜けました」という方も相当数いましたが、自分達の家庭の問題を政治に丸投げするような、卑しい真似をするものではありません。「そんな親だから、子供も引きこもるんだろ!」と言われるのがオチです。
Q27:福祉関係者が多いのは、悪いことではないと思いますが?
A27:その通りで、別段悪いことではありません。ただ、医療支援と違い、福祉支援とは「通常の社会参画が難しい人々」を対象にしていることが多いですから、引きこもり当事者がその対象となるということは、「あなたには、もうまともな社会参画は不可能なんですよ」と宣告されることと事実上同値です。それ故、将来性のある当事者ほど、福祉的要素を嫌がる傾向を持ちます。福祉関係者が多いとは、既にまともな社会復帰が不可能なので、福祉支援の対象になりかかっている当事者が多いことを示しています。
Q28:補助金とは?
A28:「福祉の対象になったら、まともな社会復帰は困難」という状況を逆手に取って、
「○○障害だから復帰は困難。だから、国は補助金を!」
のように主張し始めた人々が、Eのケースです。
Q29:「手遅れの親の会」には出ない方が良いのでしょうか?
A29:そんなことはありません。実情はきちんと認識すべきですし、全てがおかしいわけではありません。同時に、最悪どのような状況になるのか見ておくことが大切です。しかし、馴れ合いを求められたら、きちんと断るべきです。良くも悪しくも、手遅れ系の親は、自分に甘い人やバランス感覚の悪い人が多いので、後で何かと苦労することになります。「政治活動に辟易」とか「馴れ合いがしつこくて困る」のような意見は、しばしば上がってきます。
Q30:自分は厳しい態度で接しているつもりなのですが……。
A30:時々勘違いがあるのですが、「態度が厳しい」から「正しい」のではありません。「○○歳までには絶対に自立すること」「自立のための訓練は疎かにしないこと」など、基本的なスタンスを譲らないことが肝要なのであって、態度云々はそれほど重要なことではありません。
Q31:弱い父親についてですが、具体的にどのような父親がそれに当たるのでしょうか?
A31:この場合について言えば、「漫然と何年間も引きこもりを許す父親」は、その後が破綻することが分かっていながら動かないわけですから、無条件で「弱い父親」です。と、同時に「無責任な父親」です。また、「子供に理解のある父親」とは、しばしば「弱い父親」「無責任な父親」をカモフラージュした言い方です。
Q32:母子家庭についてはどう思いますか?
A32:ここの卒業生には、母子家庭の子も普通にいましたが、結局は親の哲学が子に出ているだけのことです。どの環境でも動く子は動きますし、動かない子は動きません。母子家庭でも、現実的にものを考えている親御さんは、
「うちには余裕が無いから、引きこもりは認められない」
と正面から主張しますが、哲学の無い親は、
「関係の悪化を恐れて……」
などの理由をつけて結局何も言わず、わざわざ悲劇を呼び込んでいます。結局は、問題を先送りしたツケを払わされているだけです。
Q33:経済的要素が引きこもりを生んでいる気がしますが?
A33:例えば、「中卒 35歳 職歴無し」で、
「親が年金生活に入って金もなく、どうしようもない。これは経済的困窮が原因だ!」
のように主張する当事者がいましたが、中には、アルバイトで学費を稼ぎ、大学に進学して専門教育を受けて社会に出ていく人達も普通にいます。若ければ手段はいくらでもあるのですから、若いうちから貧困を理由にするのはおかしな話ですし、手遅れになってから「金が無い!」などと主張するのは、単に無思慮に生きてきた報いがやってきただけのことでしょう。
Q34:社会情勢が引きこもりを生んでいる気もしますが?
A34:社会情勢が動かない時代などあるのでしょうか? 常時動くから、動いたなりの対策を考えなくてはいけない、というのが普通の発想ではないでしょうか。社会情勢の変化など、誰にとっても同じなのですから、社会情勢のせいにするのは「自分は社会の流れについていけなかった落ちこぼれ」と主張しているのと同じことです。
Q35:逃げ癖のある子供で困っています。
A35:逃げても親が助けてしまい、本人に支障が無いから逃げるのです。逃げても親が助けなければ、段階的に変化するでしょう。いじめの問題などは別ですが、逃げ癖の根幹には、「甘え」と「その甘えを許す親」がいることが一般的です。まず、親御さん自身が少し変わって下さい。
Q36:親の優劣ってありますか?
A36:あります。はっきりと。
Q37:この場合の優劣とは何でしょうか?
A37:線引き出来るかどうかでしょう。「○○歳になったら家を出ろ!」と言うことが出来、実際にそれを実行出来るなら十分に「優」です。出来なければ「劣」です。
Q38:子供が高校を出て今25歳です。高校を出たら仕事をするように言ってきたのですが、何もせずに家でブラブラして困っています。私は高校出てすぐに仕事をしていたので、どうしても自分と比較してしまいます。
A38:半分は本人の問題、半分は親御さんの問題でしょう。
Q39:本人の問題とは何ですか?
A39:何もしないでブラブラしていることです。成人しているのですから、問題だと思うのなら、当分の生活費だけ渡して家を追い出す位のことをするのが、親としての筋です。
Q40:なら、親の問題とは?
A40:高度経済成長期ではないのですから、今のご時世に、高卒で将来性のある仕事を見つけるのは困難です。第一、高卒の意味が今と昔とでは別物です。「高校を出たら仕事を」とのお話ですが、世情を見れば、ろくな仕事が無いこと位誰にでも分かるのですから、早いうちから勉強するよう薦める程度のことはすべきでしょう。昔の高卒は、今の中堅大卒と同じようなものなのですし。
Q41:親が高卒だと、子供の引きこもりに影響はあるのでしょうか?
A41:「高卒だから」という点はさしたる問題ではありませんが、昔と今の時代とを同列に扱うのはおかしな話です。高度経済成長期だからこそ、「金の卵」などと呼ばれて、中・高卒でも将来性のある仕事があったのであって、それが今でも同じだと考えるのは間違いです。
Q42:自分と同じ経歴で社会に出るのは無理ということでしょうか?
A42:無理ではありません。ただ、「自分が高卒だから、お前も今すぐに高卒で仕事をしろ!」と言うのは容易いですが、それは、「素手で軍人と戦え!」と言っているようなものです。取り分け勘所の良い子(頭の回転の良い子)なら、不意打ちで軍人にも勝てる(自力で好条件の仕事に就ける)かも知れませんが、実際には宝くじのようなものです。
Q43:なら、低学歴の子供が引きこもったら、その段階でアウト、ということですか?
A43:若ければ「勉強し直して専門教育へ」という道もありますが、30過ぎれば9割方アウトです。取り返しがきかないので。
Q44:だとすると、30代の引きこもりの子供を持つ親はどうしたら良いのですか? 子供がどの程度のことが出来れば十分なのですか?
A44:まず、親が期待するようなまっとうな道は既に消滅している、と見ておくことです。「子供がアルバイトで食いつなげるだけの存在になれれば、それだけで100点満点」というのが現実的でしょう。
Q45:ほとんど手は無い、ということでしょうか?
A45:残念ながら、その通りです。だからこそ、「政治的に解決を!」のように主張する人々も出て来るのです。本当に詰んでいるんですよ、30過ぎの引きこもりは。
Q46:子供が仕事を一度もしたことないまま、もう35を超えるのですが……
A46:そろそろ覚悟して下さい。どのような事情があったにせよ、問題を先送りし過ぎです。限度を越えれば、対処法も消えます。
Q47:本音を言うと、子供を家から追い出したいのですが、テレビで事件になっているように、急に殺されたりする可能性は高いのでしょうか?
A47:親子仲が悪かったり、急に叱責したりすれば、その危険性も高いでしょう。どの道危険性は高いですが、段階的に話を進めた方が良いです。
Q48:もう、全てを諦めてしまっている親御さんとかいませんか?
A48:普通にいます。子供が30過ぎると、諦めムードが漂いますし、そうなったら、後は坂道を転げ落ちるだけです。30過ぎでも対処可能な場合もありますが、希少事例です。
Q49:やるだけのことをやり尽くして諦めるってことでしょうか?
A49:いえ、それよりは、
「決定力の無い、いい加減な甘い対応」→「気付いた時には手遅れ」→「面倒になって諦めムード」
ということの方が多いです。早いうちから妥当な方向性で全力対応してダメなケースは、少なくともここではほとんど見たことがありません。
Q50:子供が引きこもり始めたら、少し早めに親も動いた方が良いってことですよね?
A50:仰る通りです。ある程度の「待ち」は有効性を持ちますが、3年待って動かない場合には、親も本気を出さないと後が大変になります。
注:当コラムについては、内容に対する厳しいご意見と同時に、ご家庭をお持ちの親御さんからの感謝の言葉、そして、不登校・引きこもりとは全く関係ないものの、問題を熱心に考えて下さる方々からの激励の言葉がございましたため、コラム末尾に追記を加えました。
参照:引きこもり 主張はどこまで 通るのか? ~引きこもりを見る社会の目~
参照: 「反対!」と 叫ぶ姿勢に 宝有り ~建設的反対意見を出す能力~
参照:不登校から安定的に大学進学するには?
追記:「不登校 引きこもり と親の責任」ご意見への回答
「子育ての参考になりました」とのご意見について
ありがとうございます。この内容については、実際に現場で苦労した引きこもり当事者の方達の実体験と反省、そして、その家庭に足りなかった要素を抽象的な形に薄めて掲載してあります。必ずしも全てが参考になるとは限りませんが、少しでもお役立て頂ければ幸いです。
偉そうなことが言えた立場ではありませんが、各家庭を100単位で見てきた者としては、「親」として最も大切なことは、学歴や年収などではなく、これまでに培ってきた「人生哲学」だと感じています。子に何かを問われたときに、例え不完全でも、「俺はこう思うぞ」「私はこう考えて生きてきたけど」のように返せること、言い換えれば、一人間としての意見を持つことが重要なようです。そしてこれは、親御さん自身による、誠実な日々の積み重ねによってしか形成されないものと思います。
私自身、父親や母親とは正面から議論したことが多々ありましたが、これは今でも誇るべき無形の財産となっています。是非、お子さんと正面から挑める、カッコいい「オヤジ」「オフクロ」になって下さい。私は、そんな「オヤジ」「オフクロ」を全面的に支持し、応援しています。
「こういった情報は、隠すことなく全面的に開示して目を醒まさせることが、当事者本人の、ひいては社会全体のためだと思います。引きこもり当事者が社会復帰出来ず、社会全体で背負わないといけないとするなら、結局は自分達普通の社会人も泥を被ることになります」とのご意見について
仰る通りかと存じます。ただ、このような話を一般に公開することはリスクも大きく、「単に反発を食らって終わり」という事態も十分にあり得ます。実際、今回多数の方がこのコラムをご覧になったようですが、必ずしも賛成意見ばかりではありません。ここも営利組織である以上、意味の無いリスクは避けたいというのが本音です。しかし、生ぬるい、耳触りの良い言葉だけでは、結局全員がダメになってしまいます。
昔から変わらず同じなのですが、このコラムに同意される方は、実際に社会生活を営んでおられる方や、引きこもりから抜けた元当事者、問題解決に熱心な親御さん方、改善意識の高い当事者等、実社会を具体的に見ている方々に多く、一方で、全面的に反対される方は、引きこもりから抜け出すことが困難な、非常に状況の悪い当事者に多い傾向があります。しかし、これは至極当然のことかと思います。
長期の引きこもりと言っても、一概におかしな人達ばかりではありませんし、やむを得ない事情のある人も、若干は存在します。そのため、この手の話を一律にゴリ押ししたいとは考えていません。こんな内容を掲載しておいてこんなことを言うのも偽善ですが、あくまで、改善意識の高い人達に対する「温かみを内包した厳しい警告」であるべきと認識しております。
「詰む」について
「『詰む』という幼稚な表現は支援側としていかがなものか?」
「『詰む』とは具体的にどのような状態を言うのか?」
についてご意見を頂きましたので、再掲載致します。
まず、「詰む」という表現を使用した理由についてですが、これはこの表現のストレート性にあります。若年層に受け入れられている表現のため、若年層全般に対して切迫した状況が端的に伝わると同時に、状況悪化に対する歯止めの一言としては妥当な表現と見ています。一般認識としては間違いなく不適切でしょうが、当事者やその関係者に実情をきちんと伝えるには、寧ろこの方が伝わりやすいと判断しております。
「まだまだ日本の社会には余裕もあるし、『詰む』等という表現で当事者を追い詰めるものではない」
のようなご意見もありましたが、確かに、長期引きこもり当事者の大半が、最低限アルバイトだけでも就けるようなら、「余裕がある」と言っても間違いないでしょう。しかし、それさえ難しい場合、とてもではありませんが、余裕があるとは言えないかと思います。(これについては、後述する職場の環境も、その理由に含まれます。)
5年ほど前に情報を集めたときでも、三分の一~半分は、数日単位の短期アルバイトすら困難のようで、仕事に耐え切れず、数時間で逃げ帰るような例が決して珍しくありませんでした。恐らく、実際に職場から逃げ出した高齢引きこもりを見かけた社会人の方もいらっしゃるかと思います。
仰る通り、「詰む」という表現には強引な要素がありますが、状況が悪化するまで無関心に放置し、何も出来なくなってから彼らの存在自体を無視するよりは、やや極端でも、早いうちに警告をかける方が、幾分誠実かと思います。ただ、この警告に対する判断は、個々人の当事者に任せることになりますので、無責任と言えば無責任ですが。
次に、具体的な「詰んだ」状況についてですが、これは「自分の力で生存することが事実上不可能」という状態を基準に話をしています。一言で言えば、「社会の中で生きられればOK。生きられなければ『詰み』」です。無論、親も年金生活に入っており、経済的バックアップはほとんど無い状態です。
もう少し具体的に言えば、以下のいずれかに該当する場合が適切かと考えています。
1:家族にも経済的余裕が無いのに、全く部屋から出られない
2:外には出られるが、仕事に就けるだけの社会性がない
3:仮に仕事に就けても、十分な所得を得るだけの継続が出来ない
特に多い(目立つ)のが2・3で、職場に行けない、面接が出来ない、或いは、引きこもりは抜けられても、仕事を継続出来ないケースです。
理由は様々ですが、基本的には「極端な体力不足」か「社会性の欠如」のどちらかです。前者の場合は鍛えれば良いのでまだ大丈夫ですが、後者の場合には、年単位の助走期間を必要とします。中学・高校から30代になるまで引きこもっていれば、概算で15年は引きこもっている計算ですし、これは人生の半分を引きこもりとして生き、社会性は中学生、下手をすれば小学生レベルという話になります。中学生、或いはそれ未満の口下手な子供に、急に30~40代の成人と同じレベルのコミュニケーション能力を要求することの難しさは、誰が見ても分かるかと思います。しかも、10年単位で他人と話をしたことがないとするなら、その場に適した表情を作ることさえ困難です。
また、長期の引きこもり当事者が就ける仕事は、概して労働環境が熾烈で、一言で言えば罵声や怒声が当たり前の、「スパルタ環境」である場合が大半です。本来なら、順当に少しずつ課題のレベルを上げ、少しずつ少しずつ社会へ慣らしていくのが適切です。しかし、そんなことまで考慮してくれる職場など、今の余裕の無い日本には事実上存在しません。この「余裕の無さ」は、普通に生活されている社会人の方が、一番良くご存じのはずです。
ある日の朝、話も出来ず、目も虚ろで、挙動一つ一つが奇妙な中年期の男性が、あなたの職場にやって来ます。ただでさえ自分の仕事で手一杯なのに、彼にまで丁寧な対応が出来るでしょうか? 恐らく、ほぼ全員が「無理だ」と感じるはずです。それどころか、何もせずに突っ立っているだけの彼の存在を、疎ましくすら感じるでしょう。
かくして、これまでの経緯からすれば、最初から継続不可能としか言いようのない就労環境下に、当事者はある日突然放り込まれるのです。
現実問題として、引きこもりから抜けるのは案外容易です。しかし、生きるだけの資金をコンスタントに手にし、社会の中に無理なく溶け込むには、多大な労力を要します。ここのハードルが極めて大きく、本人がどれほど頑張っても、そのハードル越えの途中で資金がショートしたら目も当てられません。
上記のような場合、現実的な「死」が、近接した未来のどこかで確実に発生するでしょう。公的扶助による生活保護という手もあるでしょうが、今の余裕の無い日本で「10年以上何もしてこなかった引きこもりにも生活保護を!」等と訴えれば、袋叩きにあってもおかしくないはずです。
実際、このコラムの反響を幾つかのサイトで拝見していたところ、引きこもりの生活保護受給に反対する意見を相当数見かけました。普通に社会生活を営み、納税している方々からすれば、「何故、何もしてこなかった連中を援助せにゃならんのだ?」と考えても、全く不自然ではありません。国の方向性としても、生活保護は漸次縮小する見込みですから、この選択肢は最初から期待しない方が良いかと思われます。
対応が遅過ぎたせいで自力でもカバーし切れず、かと言って、公的機関のサポートも薄いとなれば、「生きられるだけの最低限のお金」さえ手にすることが出来なくなるでしょう。これは、事実上「生存不可能」=「詰む」と言って間違いないのではないでしょうか。
尚、
「選ばなければ、何歳でも仕事なんてありますよ。本人のやる気次第ではないでしょうか?」
というご意見もありましたが、これは長期間引きこもってきた当事者には大変酷な話です。普通に生活している方からすればその通りですが、そのレベルに達するには、例えば10年単位で引きこもっていた人の場合、同様に数年単位の配慮(主に家族から)とサポートが必要でしょう。しかし、これをスムーズに行うことも、余裕の無い家庭からすれば、現実的には困難です。
以上のような事情から、丁寧に考慮した上で「詰む」という表現を使用している次第です。決して、当事者の人々を追い詰めたり、絶望させたりすることが狙いではありません。しかし、結果的にそれと近い状況を引き寄せてしまうことについては、改めて深くお詫び致します。
性質上、あまり愉快な話題ではありませんが、他にもご意見等ございましたら、そのままお送り頂きますようお願い致します。今後の運営の参考とさせて頂きます。