「いや、違うんだ。今はもう、そういう状況じゃないんだ」
と言いたい記事が一つ
「明日の学校はムリかも」と迷っている人へ 中学3年生を丸ごと休んで得られた6つの結論」
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishiishiko/20180902-00095018/
先に断っておきますが、私はこの筆者の方を毛嫌いしているわけでも、喧嘩を売りたいわけでもなく、ただ実直に、現実的要求の論点がズレ始めていることを語っておきたい訳で、その点はご承知おき下さい。
文章の内容はシンプルで、
○学校行かなくても、通信制高校とか大学とか、選択肢はたくさんあるから大丈夫。
○不登校でも、その後は仕事もあるし、普通の日常が待っているから大丈夫。
○周囲の大人達は、彼等のSOSに気付いて、相談窓口も利用しながら、命の確保を。
です。内容自体に全く嘘はなく、何一つとして否定する要因はありません。ごもっともです。
ただ、ここには決定的に足らない要素があります。記事を読んで、私も、
「ああ、やっぱりまだこの状況で止まっているんだな……」
と言わざる得ない隠れた問題点、即ち、
「結局、不登校経験者は、どのような社会人になっているのか?」
というテーマです。これは十年以上前からあり、未だにまともな解がない、厳密に言えば解はあっても、不登校経験者には都合の悪い解で、誰もが表面に出したがらない話題です。
状況を分かりやすく説明するため、かなり刺激的な話題ですが具体例を上げておきます。ここには特定の支援者を批判する意図があるわけではなく、純粋に不登校経験者の子達(解析能力に長けた子達)が、どのように支援者側を見ているのか、端的に示しているものだとご理解下さい。尚、対話で出てくる子は、今は医学部に在籍しているCARPE・FIDEMの卒業生です。
E「そう言えば、前に言ってた、居場所的なところはどうだい?」
卒「ああ、あそこはもう行ってないですよ。二、三回顔出しただけなんで」
E「何でまた? 慣れるまでは通ってればいいじゃない?」
卒「いや、いいっす。何か、いたたまれなくなるんで」
E「??? いたたまれないって?」
卒「いる人達が、ちょっと。自分が文句言えた話じゃないですけど……」
E「良く分からんな」
卒「言い方悪いけど、『この人達、大丈夫なのかな?』って。自分、学校辞めて、母親に言われてアチコチ行ってみたけど、大体どこも優しいんですよ。『大丈夫だよ、とか、心配ないよ』とか」
E「別にそれはええんでね?」
卒「まあ、そうなんですけど。でも、そこの主催者とか、ボランティアしている人とかの経歴とか、今の年齢とか、やってることとか聞くと、何か……」
E「???」
卒「言い方悪いけど、レベル低いんですよ。『大丈夫』って励ましてくれるのは嬉しいんだけど、その『大丈夫』って何? 死ななかったから大丈夫なのか、家から出られてるから大丈夫なのか……。ただ、自分が欲しい『大丈夫』って、そんなレベルじゃないんですよ」
E「ああ、そういうことね」
卒「元不登校の人とかがスタッフでいるんですけど、『仕事してないからボランティアで』とか、30歳過ぎで中卒社会経験無しとか、学歴が最高でもマーチで、しかも就活失敗とか……。自分達の体験談語るのは良いんですけど、それ全然参考にならないし。自分の失敗談聞けば、相手が安心するとでも思ってるんですかね?」
E「そこは君が批判すべき点ではないな。彼等だって、それなりの苦労はあるんだから」
卒「分かってますよ。でも、そんな人達に『大丈夫』とか言われて、Ecoさんは納得しますか? Ecoさんは経済力凄いから何とも思わないかも知れないけど、自分何も無いんですよ? 昔の高校の同期とか、今頃医学部とか東大とか早慶とか行ってて、社会でめっちゃ活躍すること分かってるんですよ。そこを、『大丈夫だよ。心配ないよ』とか言われても、こっちからすれば『あんたらの方が大丈夫じゃないだろ? 人生設計どうなってんの? 自分達が底辺化しつつあるのに、俺達現不登校の世話して悦に浸ってるだけで、自分達の問題二の次にして、大丈夫とか言ってんなよ』とか思う」
E「……」
卒「不登校とか陥ったら、結局どこかで元のルートに戻らないと、底辺でワープア確定じゃないですか? ネットで調べりゃ、そんなのすぐ分かるじゃないですか? 無教育で他より遅れてて、それでもまともな仕事あるなんて、誰が信じるんですか? 不登校じゃなくても、浪人と留年あるだけで就活に響くのに、何甘いこと言ってんの? あんた年収いくら? 社会保障どうなってんの? 厚生年金はあるの? 退職金は?」
E「気持ちは分かるが、外では言うなよ、そういうこと。僕がいつか言っとくから」
卒「それ位の分別はあります。あそこも『ありがとうございました』って言って出てきました。顔には出てたかも知れませんけど。自分、顔に出やすいんで」
E「君は賢いから、先が見えるんだろうさ。だが、人には言うな。分かっている人達だけで話せば良い」
内容が内容なので憚られますが、私は彼の意見は真っ当なものだと思っています。記事にも、
>2000円もするパフェが食べられたり
とありますが、今彼等が欲しているのは、そんな定性的な些末な話ではなく、不登校でどの程度の遅延があると、大体どの程度の学歴と就職状況で、どの程度の所得と社会保障が得られて、という定量化された現実です。完璧でなくても構いませんので、目安だけでも。せめて「30代で2,000万円台の家を建てました」なら、社会情勢を考えても、まだ安心を呼ぶでしょう。しかし、齢35になる不登校先輩が、後輩に語る「安心」の根底で「パフェ」を持ってくるようでは、逆に疑惑の温床になります。わざわざ記事にしてまで語る内容がその程度では、それ以上の誇れるものが無いかのような印象を受けてしまいます。不登校の子達は10代で子供のカテゴリに入るかも知れませんが、パフェ云々で通じる年ではありません。彼らは馬鹿でも阿呆でもなく、かなりシビアに社会を見ています。
また、
> さらに高校からは通信制高校というものがあり、月に1度から2度の登校で卒業できる学校もあります。試験だけを受けて「高校卒業」と同程度の資格が得られる制度もあります。大学も通信制大学が全国で43校もあり、いわゆるテスト競争をする「大学受験」はナシで入学できます。
とありますが、実際の実績を見れば分かる通り、通信制高校や通信制大学の卒後の就職先は、決して褒められたものではありません。第一、ロクにテストもせずに入れる教育機関に、どの程度の人間が集まるのか、容易に推察がつくではありませんか? 就職時に、採用側はどう判断するのでしょうか? 早慶や明治・立教・青山のような大学付属校ですら、就職時には付属上がりかどうかが人事側で話題になるのに、資格が同等だから「試験無しでラッキー」等という判断が通用するのでしょうか?
「道があるから大丈夫」と言いっ放しにするのではなく、本当にその道が大丈夫なのかどうか検証し、現実に先に繋がる道を提示するのが先人の義務でしょう。それこそ、万葉の昔から「苦あれば楽あり、楽あれば苦あり」の基本中の基本が、洋の東西を問わず語られている中で、流石にこれは浅慮に映ります。CARPE・FIDEMには、小学校から学校へ通っておらず、将来性を考えて医学部へ進学した子もいましたが、この子も、高校生の年齢から「社会情勢に対する考察の甘さは、結局自身の死に繋がる」と判断して学習を続けていました。見ている子は、先人達の無知さえ正確に見抜いているのです。
しかし、その辺が今の支援者側には見えていない。逆に、具体性のない立ち位置から出てくる安易な「大丈夫」が故に、かえって疑惑を生む結果になっています。
はっきり分かっているのは、今の日本で明確に階層化が進んでいる点です。昔は何となく適当でも大丈夫だった(ように見えた)かも知れませんが、今は大筋10~20代までの経歴で30代以降の流れはほぼ決まります。変えたくても、変えるルートもありませんし、変えるだけの能力を養成することが難しい。それ故、若年期の一年は大変な価値があり、頭の働く子はその点に危機感を抱いている。逆に、頭の働かない子は、後からその事実に気付くものの、気付いたときには手遅れである。
昔の不登校経験者が今は支援する側になっていて、彼等は牧歌的に「大丈夫」と優しく語りかけるのでしょう。しかし、そんな行為も段階的に意味を持たなくなってきています。本当に大丈夫だと言うなら、自分達の経済状況も含め体系化されたデータを開示する位の方が、より説得力があります。しかし、誰もそれをきちんと出さない。出したにしても、どうにも不安定さが残る立ち位置ばかり。何故なのか?
結局、不登校・引きこもりは、社会参画に不利にしか働かないということです。有利にするには、手段は二つだけ。
○何らかの教育ルートに極力早く戻る。
○何らかの分野で、自分の特技を活かして事業を始める
この程度です。しかし、後者は極めてハードルが高い。5年維持が25%、10年維持では10%しか残りません。しかも、私が見てきた不登校関係者の自営展開は、国や自治体からの補助金頼みのものが多く(NPO主体等)、気付いたら無くなっているケースも何度も見ています。NEET株式会社なんて洒落もあり、早々に潰れていましたが、不登校・引きこもりの依存体質が、ここでも問題となっていました。
元々自営業展開は成功率が低いため、一般論的には前者しか道がない。それ以外のルートを取れば、余程の幸運が無い限り、常時人並み以下の不安定さを抱えて生きることになる。詰るところ、結局は元の学校でなかったにしても、環境を変えて何らかの教育ルートに戻った方が楽ということです。それも、遅延の分だけ一段階上に上げて。
以前にも話しましたが、自殺防止の意味でのワンストップ戦略として、優しい「大丈夫」の価値は認めます。しかし、それにしては、「大丈夫」と語りかける方の側が本当に大丈夫なのかどうか疑わしく、場合によっては、「不登校先輩」そのものの生き方の善し悪しが、後輩側から問われているとも言えます。
私個人としては、「大丈夫」という言葉を語る側は、それなりの覚悟を持って語るべきだと思っています。でないと、その言葉の意味も価値も薄れ、未来のどこかで泥沼化します。「全然大丈夫じゃなかったじゃねえか!」と後輩達に言われたら、不登校先輩達は、一体何と返すつもりなのでしょうか?
少なくとも、以前私が調べた限りでは、不登校から通信制高校等を経由して社会に出た子達(つまりは、不登校の中でも中位層の群)の大半は、「まとも」とはほど遠い職場環境で仕事をしています。良くて零細中小企業の正社員(10~20%)、大半は単純労働系の派遣か契約社員(50%前後)で、アルバイト(30%前後)も普通。どれも、社会保障が脆弱で昇給もほとんど無く、待遇は中央値以下。不況期の首切りに怯えながら生きるだけで、専門職に関連する業種はまず見ません。それ以上の階層に上がっているのは、ほぼ全て中位以上の大学進学へした学生のみで、他はかなり控えめに書いても「転落人生」です。
少ない給与、乏しい社会保障、成長の無い日々。それが本当に「大丈夫」なのか? 上記のような単純労働は、既に外国人労働者に置き換わっており、日本人が行う必要性はありません。都内にいれば、コンビニの店員に外国人が多いことに驚かされるではありませんか? 先進国日本で生きる以上、ある線引きを越えた立ち位置に就くのは、いまや生存上の義務になりつつあります。目先の死を恐れるあまり当座の誤魔化しだけに終始し、別のタイミングでまた別の死、それも完全に改善策を失った上での死を叩き付けることになるのだとしたら、一体何のための支援なのか?
不登校経験者は、概して他人に甘いですが、同時に自分にも甘くなりがちで、結果、今回のような後輩からの突き上げを食らうことになります。何となくナアナアで、何となく優しくしていればそれで良しとされていた時代は既に過ぎ去っており、それ以上の具体策が求められる時期に差し掛かっていると考えます。
今回の文章の筆者の方は82年生まれで、私と同い年のようです。同じ社会を見て、同じ社会で生きてきた者として、より現実的な視点で後輩を導いてくれることを期待し、メディア関係者としての義務を果たして欲しいと強く願います。


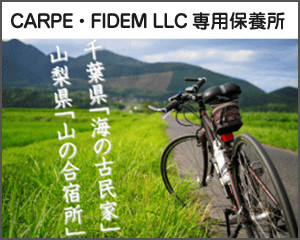
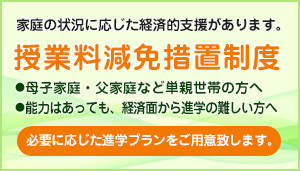
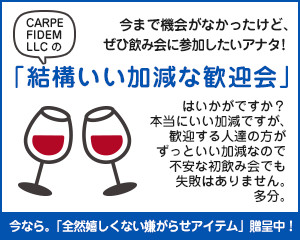
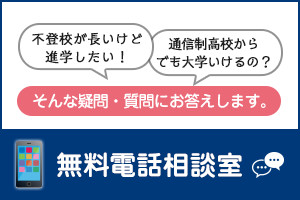
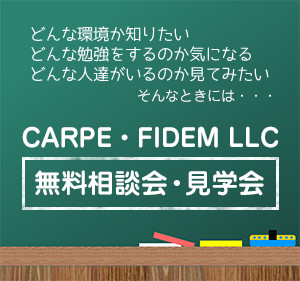
最近のコメント