不登校・引きこもり関係の仕事に関与して、かれこれ20年近く。40を手前にして、ようやく手にした小さな小休止で一息入れてみると、支援において何が大切だったのかが、自ずと見えてきます。
何はともあれ大切なのは、当事者の「自立」。少なくとも、自分一人の生活は維持出来る程度の経済力を有し、外部からの干渉を拒否出来ること。
職業柄、私は「自立」という概念の無い人々を散々見てきました。いつ打ち切られるか分からない紐付き金銭援助にビクビクしながら、他人の顔色を伺って生きる当事者の姿は、何とも惨めなものです。
惨めな存在程、執拗に人権を説きたがりますが、それは自立意識の乏しい彼らの人権が、常時脅かされている現実の裏返しでもあります。
己が信念、とまでは言いませんが、自我の領域を確定し、一主体として外界に働きかけるには、経済的自立が必須。当事者本人の気持ちを大切にするなら、何よりも重要なのが経済的自立です。
そしてもう一つは、「安寧」。安寧には、無論当事者の安寧もありますが、最優先にすべきは、家族の安寧です。
一般的に、引きこもりを抱える家庭は暗いものです。表面的には明るい家庭があったにしても、自立しない引きこもり当事者を抱え、先行きの見えない状況が続く中、その心中まで安寧が維持されているとは到底考えられません。押し黙って本音を問えば、不安の一言二言がほとばしり出るものです。
私が支援の核として最優先にしているのが、家族の安寧です。そして、家族の安寧とは、家族が引きこもり当事者の世話から解放され、家庭の構成員全員が、自分達の人生を前向きに生きていけることで、初めて達成されます。
最終的な達成までには時間もかかるため、安寧は段階的にしか生み出せませんし、通常は一進一退を繰り返すのが一般的です。しかし、未来への見通し如何の差だけでも、世話役の開放感は全く異なります。
引きこもり当事者の自立が未達の状態ならば、その安寧も仮初めであり、ある意味誤魔化しに過ぎません。しかし、その誤魔化しの中にこそ、私の培ってきた経験が生きるものと信じておりますし、誤魔化しがいつか本当の意味での安寧に繋がることを深く理解しています。仮初めの幻想がいつか現実を伴って具体化したとき、家族の幸福はいかばかりのものとなるか、容易に推察がつくでしょう。
最近、卒業生の一人が就職し、そして結婚しました。当人達はその気なので、案外すぐ子宝に恵まれるかも知れません。CARPEを卒業し、何年も経た子達から届く近況報告は、私としても大変嬉しいものです。
「普通」で良いのです。時代時代の流れに合わせ、その中で広く認知される「普通」を目標に、日々無理なく成長を続ける。普通の人々が普通に行う日々の営みに自身の活動を乗せることこそ、全くもって、無理の無い幸せではないでしょうか。
昨日は在籍生の子と一緒に、ワイン片手に、彼の薦める古いゲームのBGM鑑賞会を行いました。山梨のワインセラーの試飲室も、最近は上手く機能しています。
皆が自立し、安寧の中で飲む酒は良いものです。これからも、この平穏な日々が続くことを祈っています。

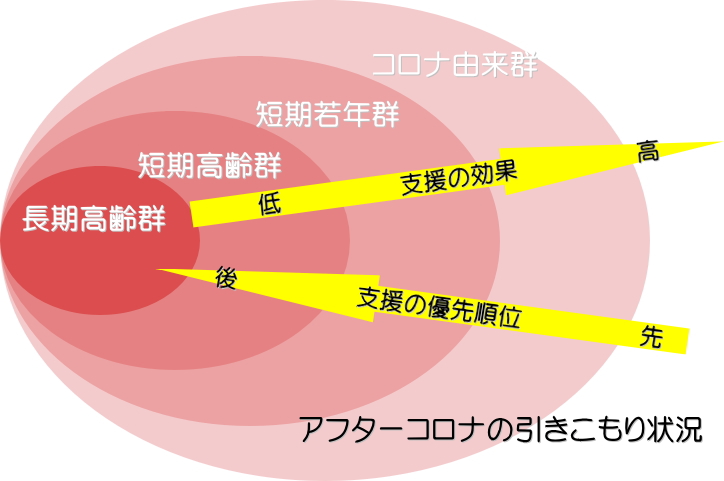

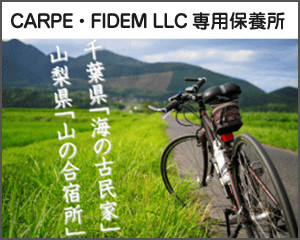
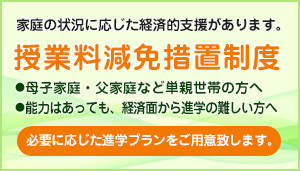
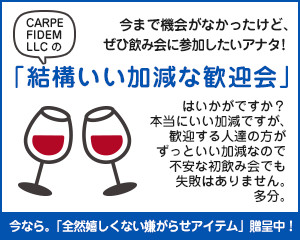
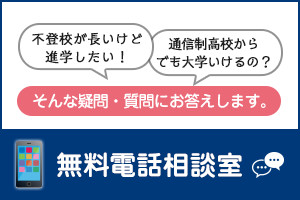
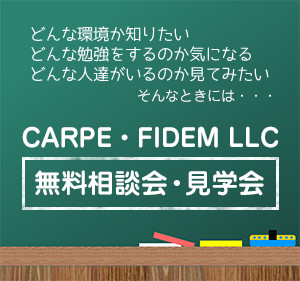
最近のコメント